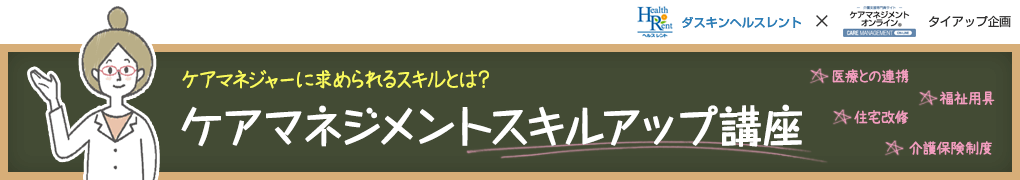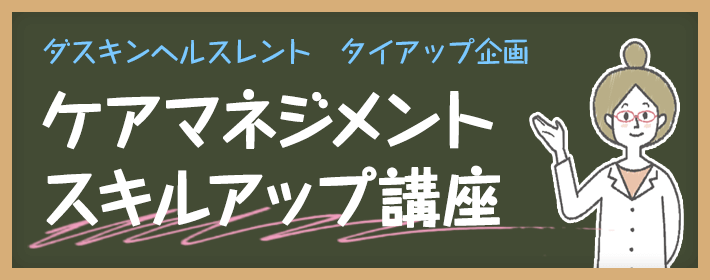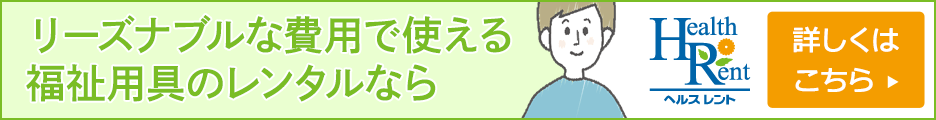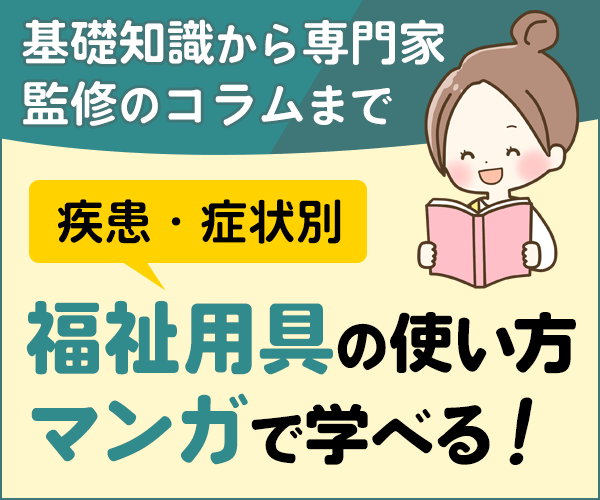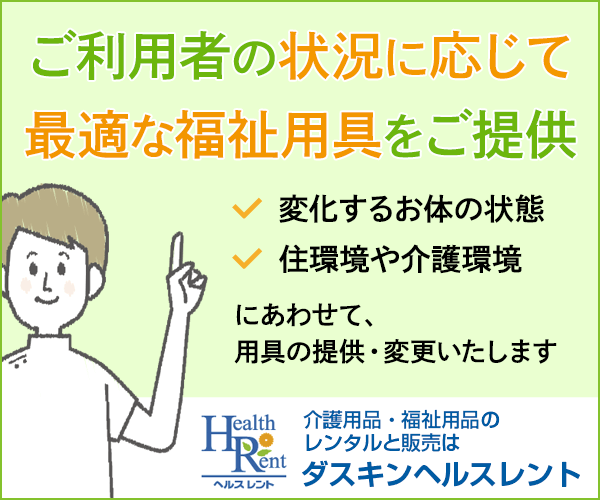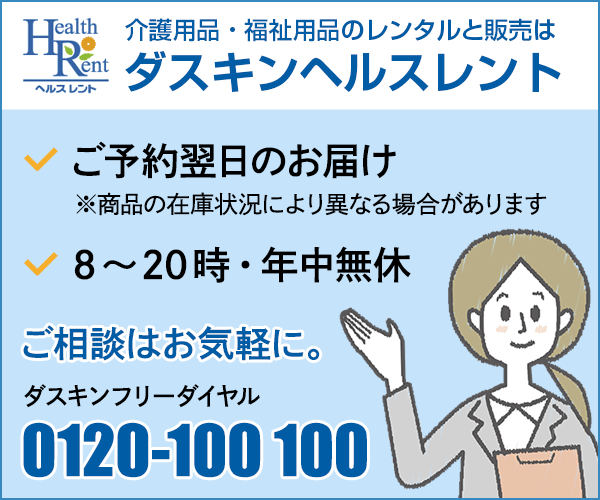白木裕子の「実践! 仕事力の磨き方」 VOL.16
ヤングケアラー問題…ケアマネジャーはどう向き合う(前編)

日本ケアマネジメント学会副理事の白木裕子先生が、介護保険制度や社会情勢に対応するためのポイントや心構えを、わかりやすく伝授する「実践! 仕事力の磨き方」。第16回は、最近、注目を集め始めたヤングケアラーとの向き合い方です。
「やっと」注目されはじめた、ヤングケアラー問題
「ヤングケアラー」。近年、新聞やテレビなどで、この言葉を目にする機会が増えました。国が全国的な調査に乗り出したこともあり、やっと、この問題に対する社会的な関心が高まってきたようです。
そう。残念ながら「やっと」です。
この点、真摯にご利用者やそのご家族と向き合い続けてきたケアマネジャーさんなら、私と同じ感想を抱かれるのではないでしょうか。実際、次のような状況に直面し、介護保険制度では何もできないことに、歯がゆい思いをされた方も少なくないのではないでしょうか。
- ご利用者のごはんを用意することはできても、そのお世話をするお子さんのごはんを用意することはできない。
- ご利用者の衣服は洗濯できても、その介護するご家族の衣服は洗濯してはならない。
いずれも、現行の介護保険制度では、「やむを得ないこと」ではあります。しかし、この手の「やむを得ないこと」が、時にはヤングケアラーを追い詰めているという現実があります。
「家族=社会資源」からの脱却が問題解決の第一歩
「利用者の自立支援のため、利用者の尊厳を守るため」という制度の原則は、間違っていません。だが、その原則だけを押し通し、家族を社会資源と位置付けてしまえば、利用者だけが快適に生活する一方、そのすぐ隣にいる家族は疲弊しきってしまう。この、ひどく非人間的で不平等な状況こそが、ヤングケアラー問題の温床といえるでしょう。
ヤングケアラーを支えるには、「家族=社会資源」という発想からの脱却が不可欠でしょう。将来的には介護保険制度の改正が必要でしょうが、現場を預かるケアマネジャーは制度改正を待たずに、「家族=社会資源」の発想から卒業しましょう。そして、今できるヤングケアラー支援を模索しましょう。
- 白木 裕子 氏のご紹介
-
 株式会社フジケア社長。介護保険開始当初からケアマネジャーとして活躍。2006年、株式会社フジケアに副社長兼事業部長として入社し、実質的な責任者として居宅サービスから有料老人ホームの運営まで様々な高齢者介護事業を手がけてきた。また、北九州市近隣のケアマネジャーの連絡会「ケアマネット21」会長や一般社団法人日本ケアマネジメント学会副理事長として、後進のケアマネジャー育成にも注力している。著書に『ケアマネジャー実践マニュアル(ケアマネジャー@ワーク)』など。
株式会社フジケア社長。介護保険開始当初からケアマネジャーとして活躍。2006年、株式会社フジケアに副社長兼事業部長として入社し、実質的な責任者として居宅サービスから有料老人ホームの運営まで様々な高齢者介護事業を手がけてきた。また、北九州市近隣のケアマネジャーの連絡会「ケアマネット21」会長や一般社団法人日本ケアマネジメント学会副理事長として、後進のケアマネジャー育成にも注力している。著書に『ケアマネジャー実践マニュアル(ケアマネジャー@ワーク)』など。
会員限定コンテンツのご案内

CMO会員限定コンテンツの「CMOたより」は、ケアマネジャーのみなさまの業務に役立つ情報を配信しています。メッセージは定期的に届きますので、ぜひログインして最新メッセージをごらんください。
※会員限定コンテンツのため、会員登録が必要です。
- ダスキンからはこんな「たより」をお届けしています
- 福祉用具に関するお役立ち情報
- 福祉用具専門相談員が語る、ご利用者様とのエピソード
- ケアマネからの福祉用具に関する疑問・質問に回答