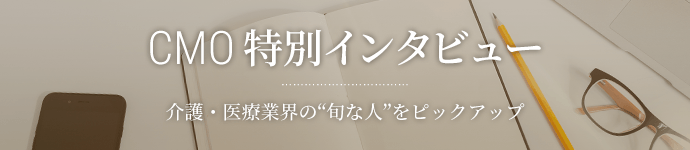
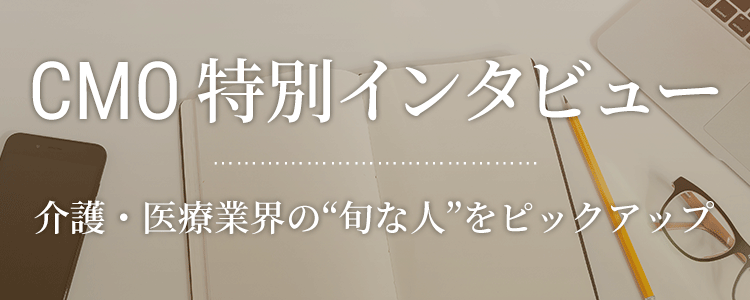
CMO特別インタビュー
※この記事は 2018年9月20日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。
オンライン診療に介護はどう関わるべきか/武藤真祐(株式会社インテグリティ・ヘルスケア 代表取締役会長)
- 2018/09/20 09:00 配信
- CMO特別インタビュー
-


2018年春の診療報酬改定に伴い、スマートフォンなどの画面越しで医師の診察を受ける「オンライン診療」が保険適用となった。一見、介護業界には関係のない話のように映るが、今後、在宅医療での普及が進めば、ケアマネジャーが担当する利用者にも影響してくるだろう。介護は、オンライン診療にどう関わるべきなのか―。オンライン診療システム「YaDoc(ヤードック)」の開発を手掛ける「インテグリティ・ヘルスケア」(東京都中央区)の代表取締役会長で、在宅医でもある武藤真祐氏に話を聞いた。
―保険適用から半年近くが経ちました。どのような手応えを感じていますか。
幾つかの見方がありますが、診療報酬の要件や国のガイドラインが厳しい中で始まったため、現時点では、当初想定されていたほど、オンライン診療の導入が進んでいないのは事実だと思います。こうした中、私たちは、さまざまな企業と連携し、普
……
スキルアップにつながる!おすすめ記事
このカテゴリの他の記事
こちらもおすすめ
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。





