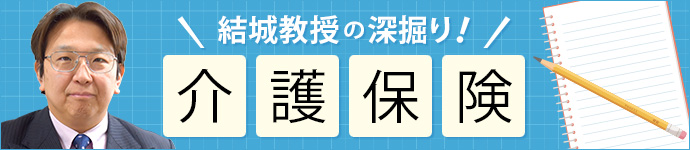
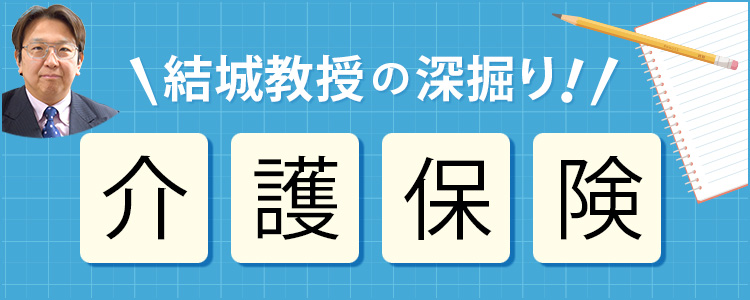
結城教授の深掘り!介護保険
※この記事は 2021年8月10日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。
居宅には“とばっちり”⁉ どう向き合う、新プラン検証
- 2021/08/10 09:00 配信
- 結城教授の深掘り!介護保険
- 結城康博
-


10月開始の新プラン検証の概要
今年10月から、新たなケアプラン検証制度が実施される。今回の検証における介護サービスのターゲットは、やはり訪問介護だ。
現行制度でも、生活援助中心型の訪問介護が一定の回数に達した場合、ケアプランを市町村に届け出なければならない。
10月から導入される制度は、生活援助だけでなく身体介護も対象だ。しかも、各事業所を市町村自らが検証する。そして、該当するケースがある居宅介護支援事業所は、ケアプランの届け出が求められる。
基準は、「事業所全体のサービス費の総額が区分支給限度基準額の7割以上を占める」こと。さらに「事業所全体のサービス費の総額の6割以上が訪問介護」であること(図1)。この両方の基準に合致した事業所が届け出の対象となる。
実際の検証対象はレアケース
ただ、区分支給限度額に対するサービスの平均利用率はそれほど高くない。特に、
……

- 結城康博
- 1969年、北海道生まれ。淑徳大学社会福祉学部卒、法政大学大学院修了(経済学修士、政治学博士)。介護職やケアマネジャー、地域包括支援センター職員として介護系の仕事に10年間従事。現在、淑徳大学教授(社会保障論、社会福祉学)。社会福祉士や介護福祉士、ケアマネジャーの資格も持つ。著書に岩波ブックレット『介護職がいなくなる』など、その他著書多数がある。
スキルアップにつながる!おすすめ記事
このカテゴリの他の記事
こちらもおすすめ
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。





