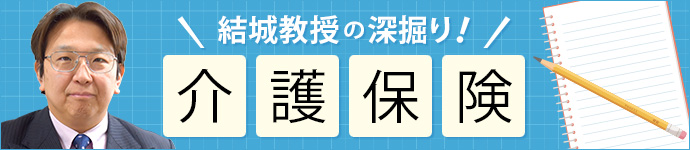
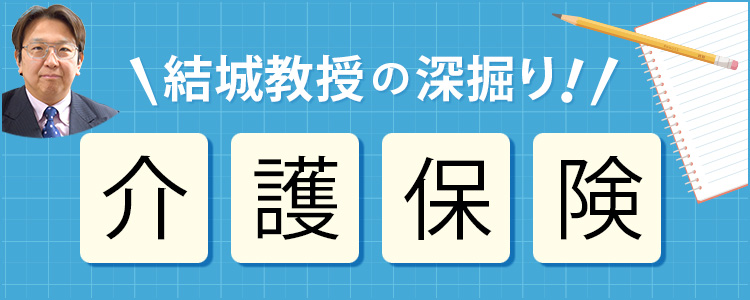
結城教授の深掘り!介護保険
厳しい内容ばかりの財務省の提案、実現しそうなのは?-その可能性を考える
- 2022/05/25 09:00 配信
- 結城教授の深掘り!介護保険
- 結城康博
-


財務省が改正で求める5つのポイント
いよいよ、次の介護保険法改正を見据えた議論が始まった。注目されているのは、4月13日に示された財政制度等審議会(財政審、財務大臣の諮問機関)での提案だ。
財政審での提案の主なポイントは、次の5点だ。
1:「利用者2割負担の対象範囲拡大」
2:「ケアマネジメントの利用者負担の導入」(ケアプラン有料化)
3:「軽度者サービスの地域支援事業への移行」
4:「介護保険施設の多床室の室料負担の見直し」
5:「経営の大規模化・協働化」
この中でも1、2、3については過去、何度となく議論されてきたことだ。読者の中には「またもや、やるやる詐欺?」と感じている人も多いだろう。また、「どうせ今回も実現されないだろう」と、考える人も少なくないはずだ。
しかし、私は次期改正においては、この5つのテーマのうち、1つもしくは2つは実現されると考える。理
……

- 結城康博
- 1969年、北海道生まれ。淑徳大学社会福祉学部卒、法政大学大学院修了(経済学修士、政治学博士)。介護職やケアマネジャー、地域包括支援センター職員として介護系の仕事に10年間従事。現在、淑徳大学教授(社会保障論、社会福祉学)。社会福祉士や介護福祉士、ケアマネジャーの資格も持つ。著書に岩波ブックレット『介護職がいなくなる』など、その他著書多数がある。
スキルアップにつながる!おすすめ記事
このカテゴリの他の記事
こちらもおすすめ
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。





