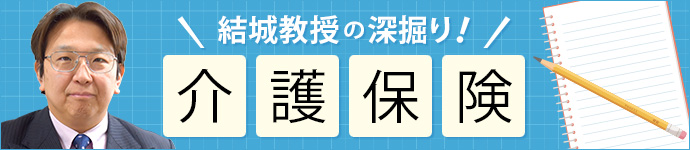
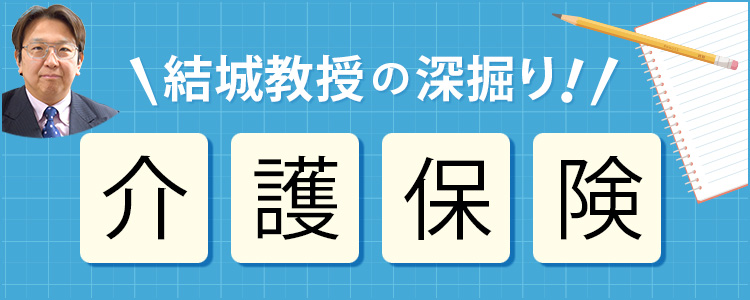
結城教授の深掘り!介護保険
基本報酬を「フラット」にして、介護予防プランを居宅介護支援へ!
- 2022/09/30 09:00 配信
- 結城教授の深掘り!介護保険
- 結城康博
-


2024年度の介護保険法改正に向けた議論が続く社会保障審議会介護保険部会で9月12日、注目すべきテーマが掲げられた。
「地域包括支援センター(包括)の業務負担を軽減するため 、居宅介護支援事業所が介護予防支援を直接担うことができるようにすべきか」である。
包括職員の「重荷」となっている介護予防プラン
同部会の参考資料によれば、包括の職員が負担超過と感じる業務のトップは「介護予防(要支援1・2)」。半数以上が負担超過と感じていた。他の業務では、負担超過と答えた職員が4割に達していないことを思えば、包括の職員にとって介護予防プランが、かなり重い負担となっていることは間違いない。=表=
地域包括支援センターにおける負担超過(過負担)業務(複数回答)
1
介護予防プラン(要支援1・2)
55.7%
2
総合相談支援業務
38.2%
3
……

- 結城康博
- 1969年、北海道生まれ。淑徳大学社会福祉学部卒、法政大学大学院修了(経済学修士、政治学博士)。介護職やケアマネジャー、地域包括支援センター職員として介護系の仕事に10年間従事。現在、淑徳大学教授(社会保障論、社会福祉学)。社会福祉士や介護福祉士、ケアマネジャーの資格も持つ。著書に岩波ブックレット『介護職がいなくなる』など、その他著書多数がある。
スキルアップにつながる!おすすめ記事
このカテゴリの他の記事
こちらもおすすめ
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。





