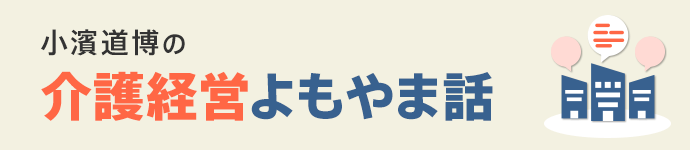
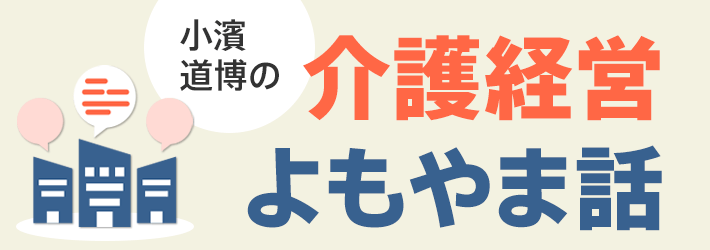
小濱道博の介護経営よもやま話
居宅にも影響、財務状況の届け出義務化
- 2022/11/30 09:00 配信
- 小濱道博の介護経営よもやま話
- 小濱道博
-


厚生労働省は先日、2024年度(令和6年度)の介護保険法改正について審議する社会保障審議会介護保険部会で、新たな財務状況の“見える化”を提起した。社会福祉法人や障がい福祉事業者に対しては、既に財務諸表の公表を課しているが、これまで対象外だった介護サービス事業者についても同様に財務状況の公表を検討するとしたのだ。
この点については、政府の経済財政運営の指針「骨太の方針2022」や、財政制度等審議会(財務大臣の諮問機関)財政制度分科会において既に示されていた。
同省はまた、介護サービス情報公表制度において、各施設・事業所の従事者1人当たりの賃金なども公表の対象とするとした。既に職種別の従事者の数や経験年数などが公表されていることを踏まえての提案で、これが実現する可能性は高いと言える。
さらに、介護サービス事業者に対して、財務諸表などの経営に関する情報を定期的に都道府県知事に届
……

- 小濱道博
- 小濱介護経営事務所代表。株式会社ベストワン取締役。北海道札幌市出身。全国で介護事業の経営支援、コンプライアンス支援を手掛ける。介護経営セミナーの講師実績は、北海道から沖縄まで全国で年間250件以上。個別相談、個別指導も全国で実施。全国の介護保険課、介護関連の各協会、社会福祉協議会、介護労働安定センター等主催の講演会での講師実績も多数。C-MAS介護事業経営研究会・最高顧問、CS-SR一般社団法人医療介護経営研究会専務理事なども兼ねる。
スキルアップにつながる!おすすめ記事
このカテゴリの他の記事
こちらもおすすめ
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。





