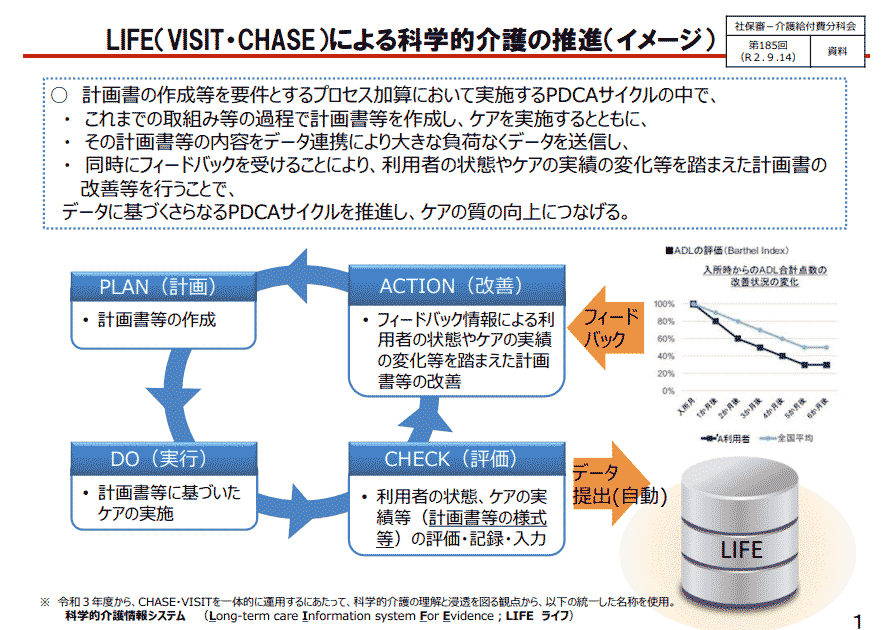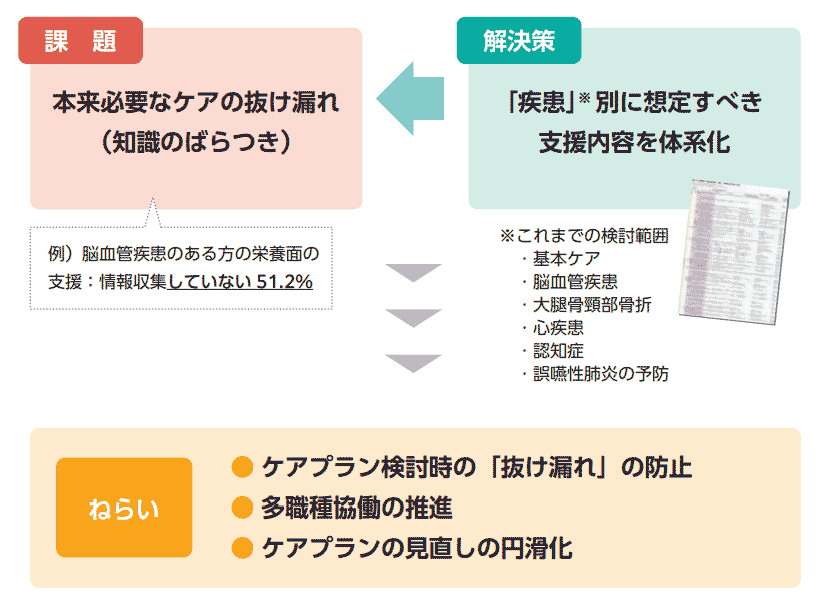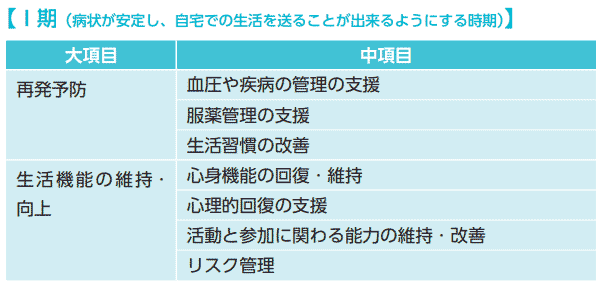医介マーケティング通信
「医介マーケティング通信」のバックナンバーをご覧いただけます。
※こちらに掲載されている情報は、メルマガ発行当時のものです。
処方増の近道はジャンケン?新たなDTCマーケティングをご提案【医介マーケ08】
(2021/7/29配信)
|
|
| 医介マーケティング通信(vol.8)のみどころ ・ 科学的介護とケアマネジメント指針 ・ 地域包括ケアシステムにおけるケアマネジャーの立ち位置[勉強用スライド②] ・ 処方増の近道はジャンケン?新たなDTCマーケティングをご提案 |
| 大変お世話になっております。 株式会社インターネットインフィニティー webソリューション部の門脇です。 医療と介護の両軸でマーケティングを考えるメルマガ「医介マーケティング通信」の第8号をお届けいたします。 ●科学的介護とケアマネジメント指針 私が社会人になった頃、医学界では「科学的根拠に基づいた医療(EBM)」のムーブメントが起きていたように記憶しています。今ではすっかり「常識」となり、あえてEBMと強調されると違和感すら覚えるのですが、私だけでしょうか…? さて、遅ればせながら、介護の世界にもやっと「科学的裏付けに基づく介護(科学的介護)」のムーブメントが訪れました。国は「科学的介護情報システム(LIFE)」の運用を通じてPDCAサイクルを回し、ケアの質を高めることを目指し、介護報酬の加算などで現場の意識を変えようとしています。 |
|
|
|
| ここで示されている「適切なケアマネジメント手法」は2階建ての構造であり、1階部分は高齢者の機能・生理を保つために疾患や状態によらず共通して重視すべき「基本ケア」です。そして2階部分が疾患に応じて特に留意すべき「疾患別ケア」となっています。 「疾患別ケア」は現状で5つの疾患が取り上げられています。 ・脳血管疾患 ・大腿骨頸部骨折 ・心疾患 ・認知症 ・誤嚥性肺炎の予防 例えば、心疾患の疾患別ケアの項目は下記のようになっています。 |
|
| これらを医療側と協働して実施することが、ケアマネジャーには求められています。これまで介護の場では食事や運動など、生活機能の維持・向上に重きが置かれてきたきらいがありますが、今後は再発予防として疾病・服薬管理も大きな柱となります。
EBMの登場により医学・医療が変わったように、今後、介護の世界も進歩するはずです。我々は、いまその入口に立っているのだと思っています。 ●地域包括ケアシステムにおけるケアマネジャーの立ち位置[勉強用スライド②] 介護が多職種連携をするときに、ハブの役割を果たすのはケアマネジャーです。 |
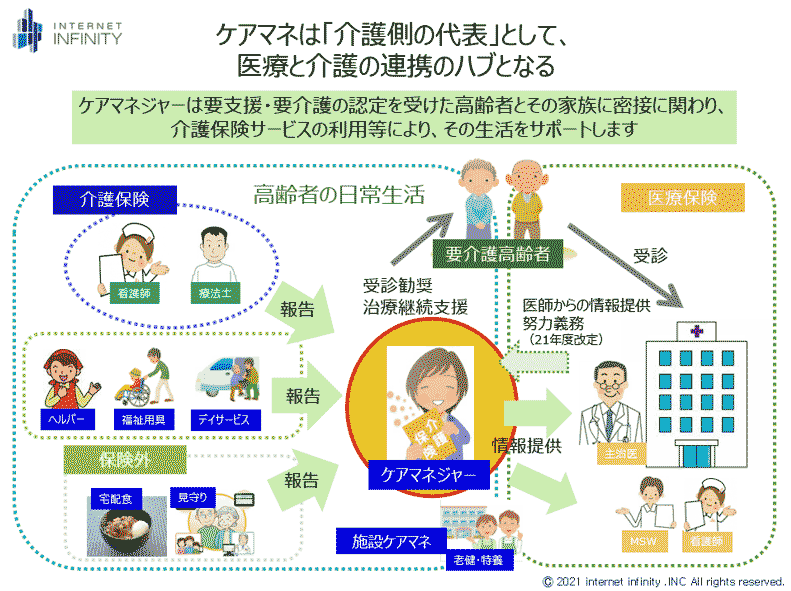 |
|
このスライドは私どもが介護業界について説明する際によく使っているものです(※ご自由に転載いただいてOKです)。 介護現場では、介護保険を用いたサービス(訪問介護・看護、福祉用具、デイサービスなど)のみならず、保険外のサービス(宅配食、見守りなど)も駆使して要介護者の生活を支えています。それらは基本的にケアマネジャーが作成したケアプランに基づき実施されます。 介護保険サービス提供者はケアマネジャーに報告する義務があり、おのずとケアマネジャーは介護側の代表者として、医療側に情報提供する窓口(ハブ)として機能します。逆に、医療側が介護側へ情報提供する際もケアマネジャーが対応することになります。 ●処方増の近道はジャンケン?新たなDTCマーケティングをご提案 とはいえ、ケアマネジャーが医師に気軽に意見したり、情報を求めたりすることは、実際は難しいことです(このメルマガをご覧の方々なら、容易にイメージできるのではないでしょうか)。多職種連携のメンバーはみな平等!気兼ねや忖度は不要!!……というのが理想の姿ではあるのですが、現実はそうはいきません。 ……この医師とケアマネの力関係について、当初は多職種連携の妨げになるのではないかと考えていたのですが、このごろ少し考えが変わりました。 医師とケアマネの2者だけを見ていると、医師が必ず勝ってしまうのですが、そこに要介護者・家族を加えた3者で考えると、新たな可能性が見えてきます。この3者の相互作用は、ジャンケンの形で整理することができます。 |
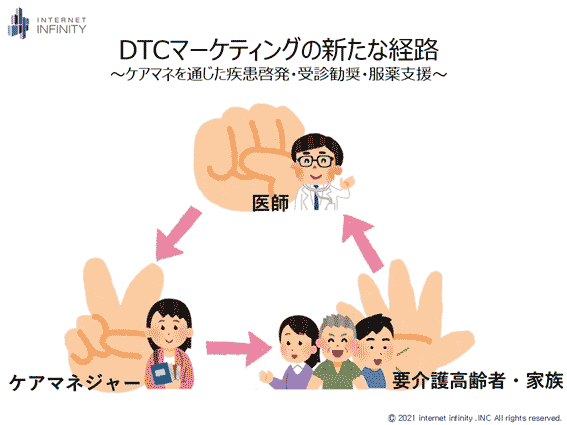 |
| 上記の図のように、ケアマネジャーは医師には弱いですが、要介護高齢者やその家族からは信頼を得ており、影響を及ぼしやすい立ち位置にいます。そして、患者や家族のリクエストを医師は無視することができません。
私たちは、この力関係をうまくDTCマーケティングに応用できないかと検討しています。すなわち、ケアマネジャーを通じて要介護高齢者・家族へ疾患啓発、受診勧奨、服薬支援に関する情報提供を行うことで、要介護者・家族が自らの意思で医師に相談し、より適切な医療につながるのではないかと考えています。
この他にも、薬が飲みにくい、効いていない気がする、副作用かもしれない、医師が気づいていない症状がある等々、色々なケースがあり得ると思います。 もちろん、ケアマネジャーが医師に直接伝えることができればそれがベストなのですが、人間関係や内容によっては、本人や家族から言ってもらった方が角が立たずにうまくいくこともあるのではないでしょうか。 この図式に、疾患啓発や受診勧奨、服薬支援を当てはめていくことで、新たなDTCマーケティングができるのではないかと考えております。 |
| もしこれにご興味がありましたら、ブレストレベルのお話でも結構ですので、ディスカッションの機会をいただけますと幸いです。ぜひ下記のフォームからお問い合わせください。 | |
ここまでお読みくださり、誠にありがとうございました! |
「医介マーケティング通信」購読のご案内
あなたも医療介護連携についての最新情報を受け取りませんか?登録は1分、購読は無料です。