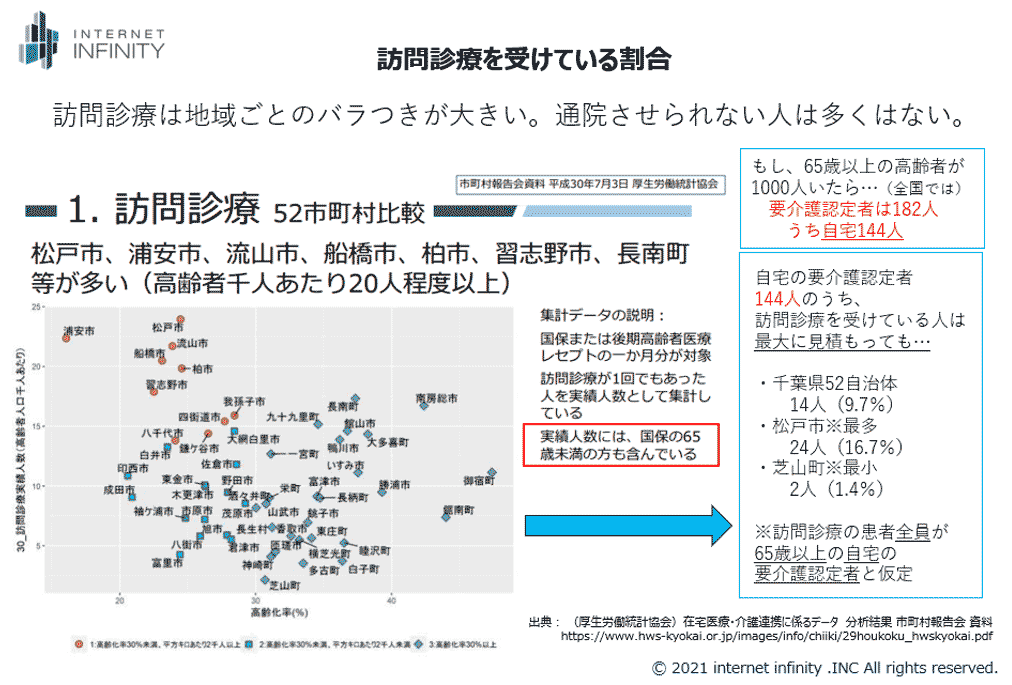医介マーケティング通信
「医介マーケティング通信」のバックナンバーをご覧いただけます。
※こちらに掲載されている情報は、メルマガ発行当時のものです。
在宅医・訪問看護師を狙う「限界」/原因疾患別の要介護度データ【医介マーケ11】
(2021/11/1配信)
|
|
| 医介マーケティング通信(vol.11)のみどころ ・ あの自治体でも?思いのほか少ない訪問診療[勉強用スライド⑤] ・ 在宅と施設とで要介護度を比べてみました[勉強用スライド⑥] ・ 要介護度が高いのは心疾患?それとも認知症?[勉強用スライド⑦] |
| 大変お世話になっております。 株式会社インターネットインフィニティー webソリューション部の門脇です。 医療と介護の両軸でマーケティングを考えるメルマガ「医介マーケティング通信」の第11号をお届けいたします。 ●あの自治体でも?思いのほか少ない訪問診療[勉強用スライド⑤] 最近、ありがたいことに複数の製薬企業などから面談の機会を頂戴しております。そこでよく聞かれるのが「介護現場にアプローチするなら、ケアマネジャーではなく訪問看護師の方がいいのではないか」といったお声です。 これは医療側に軸足を置いている方にとってはごく自然な考え方だと思いますが、現実をご紹介すると「なるほど、だからケアマネジャーへのアプローチを優先するのか!」と納得していただけます。 今回はそのことをよく示す資料をご覧に入れたいと思います。 |
|
|
| ●在宅と施設とで要介護度を比べてみました[勉強用スライド⑥] では、なぜ未だにこのような状況になっているのでしょうか? 訪問診療を受けたくても医療リソースが少なく、何とかして通院しているような高齢者が多いのでしょうか? そのような人もいるかもしれませんが、主な理由としては「そもそも在宅の高齢者は要介護度が高くない」ということが考えられます。 |
 |
|
上のスライドは在宅と施設の要介護度を比較したものですが、施設よりも在宅の方が要介護度は低いことが一目瞭然かと思います。 要支援1~要介護2というのは、杖や歩行器を使うなどして自力で多少なりとも移動できることが多いので、家族や介護関係者の支援を受けながら通院しているのだと考えられます。これは外出や運動・リハビリの良い機会にもなっています。 逆に要介護3以上になると自力での移動が大変になってきますし、自宅での介護も負担が増してきます。そのため、施設入居へ切り替える人が多くなり、結果として施設の要介護度が高くなるという仕組みです(ちなみに特養の入居条件は要介護度3以上です)。 ●要介護度が高いのは心疾患?それとも認知症?[勉強用スライド⑦] このデータに関連して、もう一つ面白いスライドをご紹介します。要介護認定が付いた主な原因疾患別に、現在の要介護度を見たグラフです。 |
 |
| ぜひご興味のある疾患の棒グラフをじっくりご覧ください。一番下の棒グラフが全体の要介護度の比率を表していますので、それと比較すると分かりやすいかもしれません。 要介護度は、生活における支障がどれだけあるかで決まります。必ずしも、一般的にイメージされている「疾患の重篤さ」に当てはまらないのが興味深いところです。例えば、認知症と脳血管障害(脳卒中)や心疾患(心臓病)を比較すると、医療的な観点からは脳卒中や心臓病の重大性が高いように思えますが、要介護度で比較すると認知症の方が明らかに高いということが見て取れます。 このことからも、認知症以外の疾患では要介護度は比較的低いために、自宅での療養を続けており、かつ訪問診療も受けていない可能性が高いと言えるのではないでしょうか。つまり、このデータも「介護現場にアプローチするなら、在宅医や訪問看護師ではなくケアマネジャーの方がいい」ということを裏付けるものだと考えています。 今回は勉強用スライドを3枚ご紹介させていただきました。このスライドは製薬企業向けの介護マーケット勉強会で使用しているものです。もし勉強会にご興味がありましたらどうぞお気軽にお声掛けください。 |
|
|
|
ここまでお読みくださり、誠にありがとうございました! |
「医介マーケティング通信」購読のご案内
あなたも医療介護連携についての最新情報を受け取りませんか?登録は1分、購読は無料です。