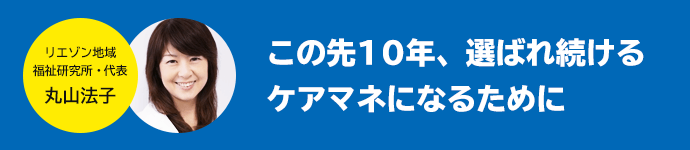

この先10年、選ばれ続けるケアマネになるために
※この記事は 2019年7月29日 に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。
選ばれるケアマネに共通すること
- 2019/07/29 09:00 配信
- この先10年、選ばれ続けるケアマネになるために
- 丸山法子
-


前回のコラムでは、利用者がケアマネジャーを選ぶ時代になるのであれば、「選ばれる存在になる」ことをケアマネ自身が選択するのはどうでしょうかとお伝えしました。
とはいえ、「サービス事業所と同一の居宅で」「自宅近くの居宅でいい」という利用者には、あてはまらない話かもしれません。目の前の利用者の実情を考えたとき、そう大きな変革はなさそうだと見ているケアマネも少なくないようです。
でも、改めて考えてみてください。あなたの利用者が、「近場でいい」「デイと同じなら便利でいい」「誰でもいい」などという、安易な判断基準で、あなたを選んでいるとしたら…?そして、そんな判断基準が、ケアプランが有料化になった後も、ずっと通用すると確信を持って言い切れるでしょうか。
強まっている「ケアマネを選ぶ潮流」
残念ながら、そうした安易な判断基準は、どんどん通じにくくなっていくでしょう。仮にケアプランの有
……

- 丸山法子
- 一般社団法人リエゾン地域福祉研究所 代表理事。人材育成、パーソナル・コーチングセッションなどの管理者研修、対人援助技術の勉強会、コミュニティづくりや地域福祉に関するセミナーなど年間100本以上の研修・セミナーを手掛ける。社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、生涯学習開発財団認定マスターコーチ
スキルアップにつながる!おすすめ記事
このカテゴリの他の記事
こちらもおすすめ
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。





