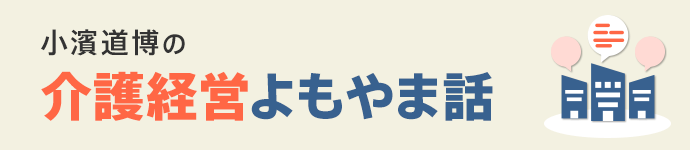
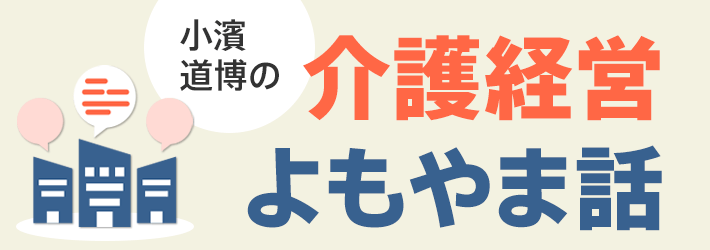
小濱道博の介護経営よもやま話
居宅は無関係?!現場の役割分担を考える
- 2022/12/28 09:00 配信
- 小濱道博の介護経営よもやま話
- 小濱道博
-


国は介護保険制度の中で、ICT(情報通信技術)の活用を推進している。その最も大きな理由が、介護業界における慢性的な人材不足だ。問題の根底にあるのが、日本人の出生率の低下であり、国内の労働人口の減少である。
日本の人口構造は、年齢が下がるに連れて減少するため、逆三角形で表される。学校を卒業後に就業する若者が減る一方、定年退職などで仕事をリタイアする高齢者は増えている。国内の労働人口は減少の一途をたどっており、改善の兆しは見えない。
これに対して、介護を必要とする高齢者の数は増え続けており、2040年にはおよそ69万人の介護職員の不足が見込まれている。
介護職員の業務の効率化などを図るため、厚生労働省は制度改正によって、ICT機器の活用を推進してきた。業務の明確化と役割分担のために見守りセンサーを、記録・報告様式の工夫のために介護記録ソフトを、情報共有の効率化のためにインカム
……

- 小濱道博
- 小濱介護経営事務所代表。株式会社ベストワン取締役。北海道札幌市出身。全国で介護事業の経営支援、コンプライアンス支援を手掛ける。介護経営セミナーの講師実績は、北海道から沖縄まで全国で年間250件以上。個別相談、個別指導も全国で実施。全国の介護保険課、介護関連の各協会、社会福祉協議会、介護労働安定センター等主催の講演会での講師実績も多数。C-MAS介護事業経営研究会・最高顧問、CS-SR一般社団法人医療介護経営研究会専務理事なども兼ねる。
スキルアップにつながる!おすすめ記事
このカテゴリの他の記事
こちらもおすすめ
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。





